食生活改善普及運動とは?
厚生労働省では、国民一人ひとりの食習慣の見直しや改善を促進することを目的として、毎年9月1日から30日までの1か月間を「食生活改善普及運動月間」としています。
令和7年度テーマ「まずは毎日、あと一皿ずつ野菜と果物をプラス」
健康日本21(第三次)では栄養・食生活の改善が、生活習慣病の予防のほか、生活機能の維持・向上にも重要とされています。
適切な量と質の食事を摂取する観点で、「バランスの良い食事をとっている者の増加」、「野菜摂取の増加」、「果物摂取の増加」、「食塩摂取量の減少」等を目的とした取り組みを推奨しています。
1. バランスよく食べよう!
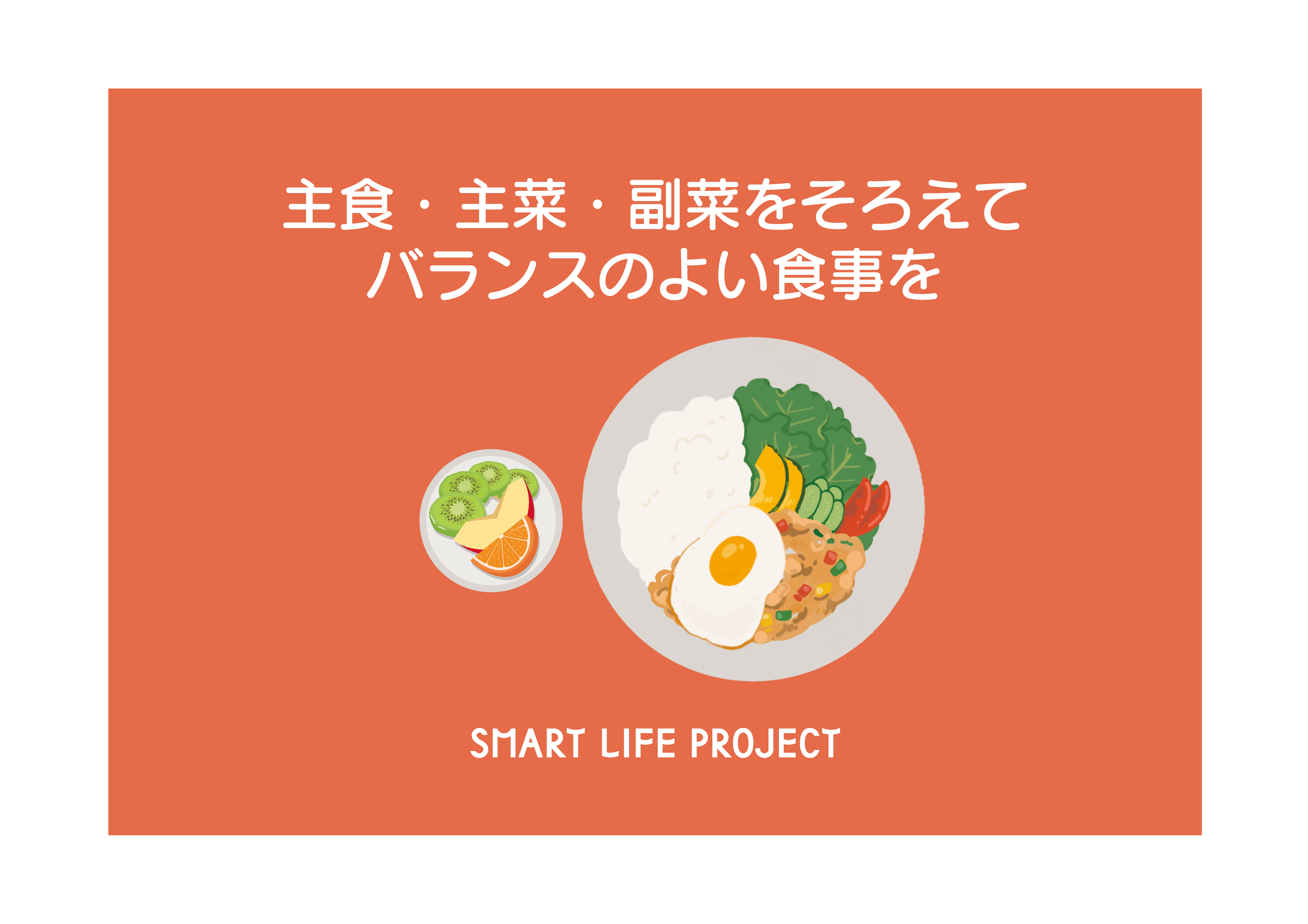
| 主食 | ごはん・パン・麺など | 生きるためのエネルギー源 |
| 主菜 | 肉・魚・卵・大豆製品など | 筋肉の材料 |
| 副菜 | 野菜・海藻・きのこなど | ビタミンや食物繊維の供給源 |
この3つを組み合わせることで、栄養の偏りを防ぎ健康的な食事に近づけることができます。
毎食そろえることを意識してみましょう。
主食:主菜:副菜の割合を3:1:2とすると、よりバランスが整います!
2. 野菜をもう1皿食べよう!
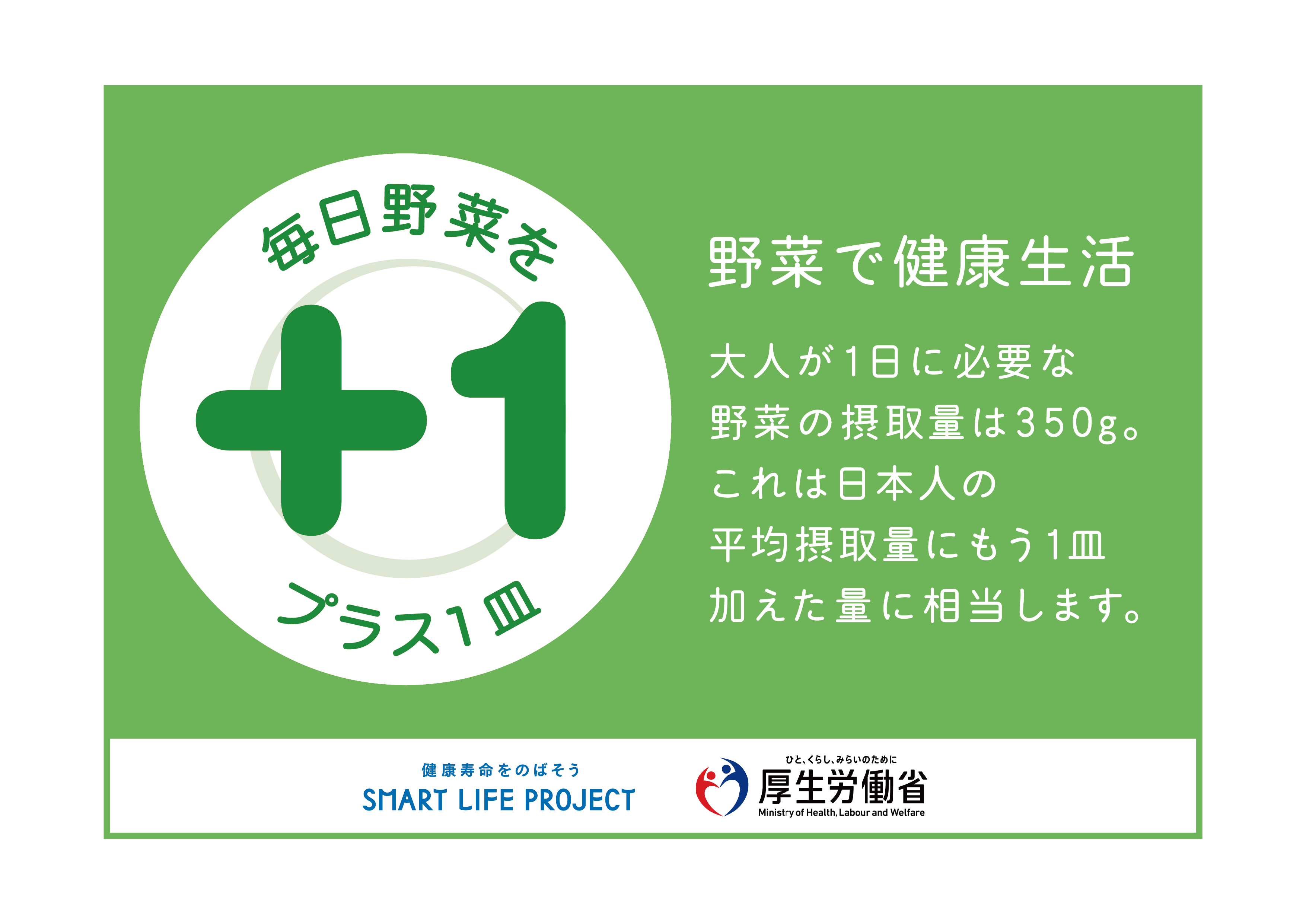
日本人の1日の野菜摂取量は目標の350gに対し、実際に食べている量は250g前後です。
目標量との差を埋めるためには、あと1皿分の野菜料理が必要です!
野菜のビタミン、ミネラル、食物繊維は体のいろいろな働きをサポートしてくれます。
その中でも強い抗酸化作用を持つβ-カロテンやビタミンC、ビタミンEは、体の老化を防いでくれる効果もあります。
副菜を一皿プラスしたり、汁物を野菜たっぷりにするなど、毎日の食事に野菜をプラスしましょう!
健康子育て課には、簡単に1日の野菜摂取量を測定する機械があります。
誰でも使えますので、気軽にお試しください!
3. 果物を食べよう!
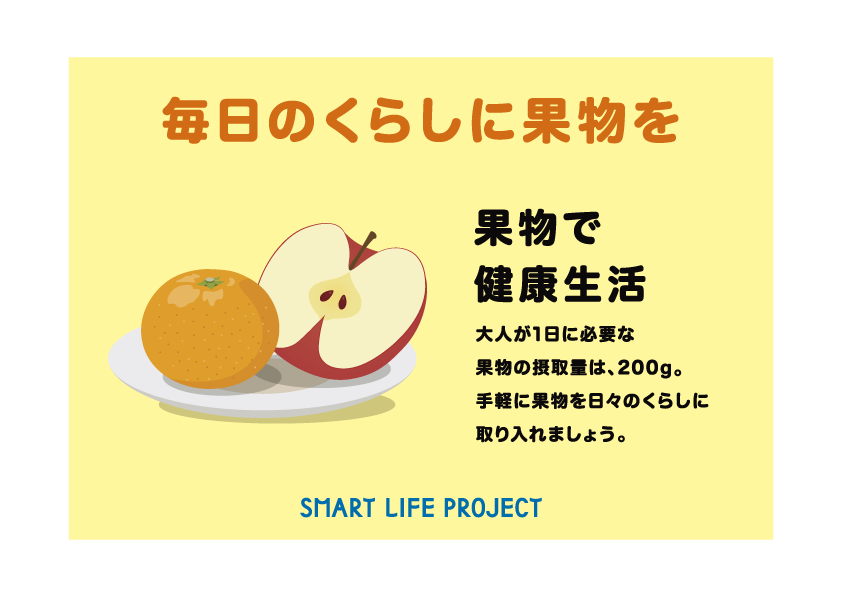
1日200gが目標です。
果物に含まれるビタミンCやカリウム、食物繊維は生活習慣病の予防にも役立ちます。
間食や朝食に果物を取り入れる習慣をつけましょう。
果物200gの目安は
りんご1個、キウイ2個、バナナ2本、みかん2個、柿1個、などです。
4. おいしく減塩しよう!
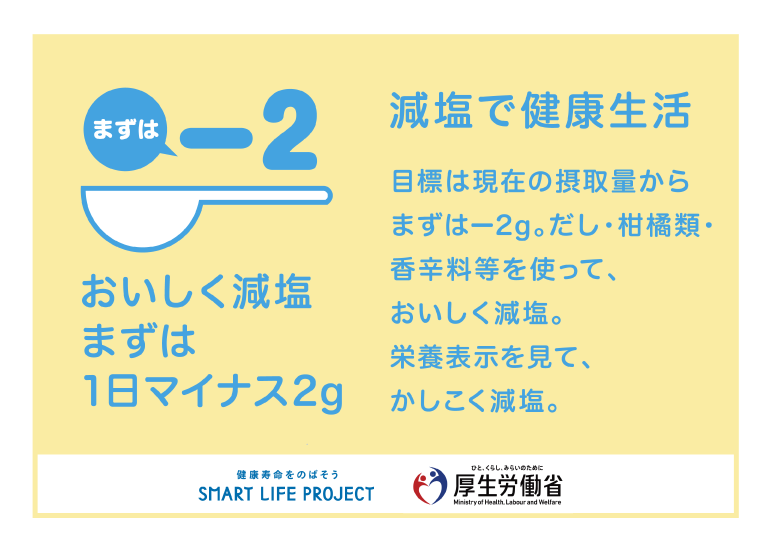
食塩摂取量の目標は、男性7.5g、女性6.5g未満ですが、
実際には男性10.5g、女性9.5gの食塩を摂取しています(2022年国民健康・栄養調査より)。
食塩の摂りすぎは、高血圧に影響します。
ちょっとした工夫で、1日-2gの減塩を目指しましょう!
【減塩のための工夫】
- 調味料は「かける」から「つける」へ
- 味噌汁などの汁物は具沢山に
- だしや香辛料を活かす
- 減塩調味料を取り入れる
- 麺類の汁は飲まずに残す
5. まいにちの暮らしに牛乳を!
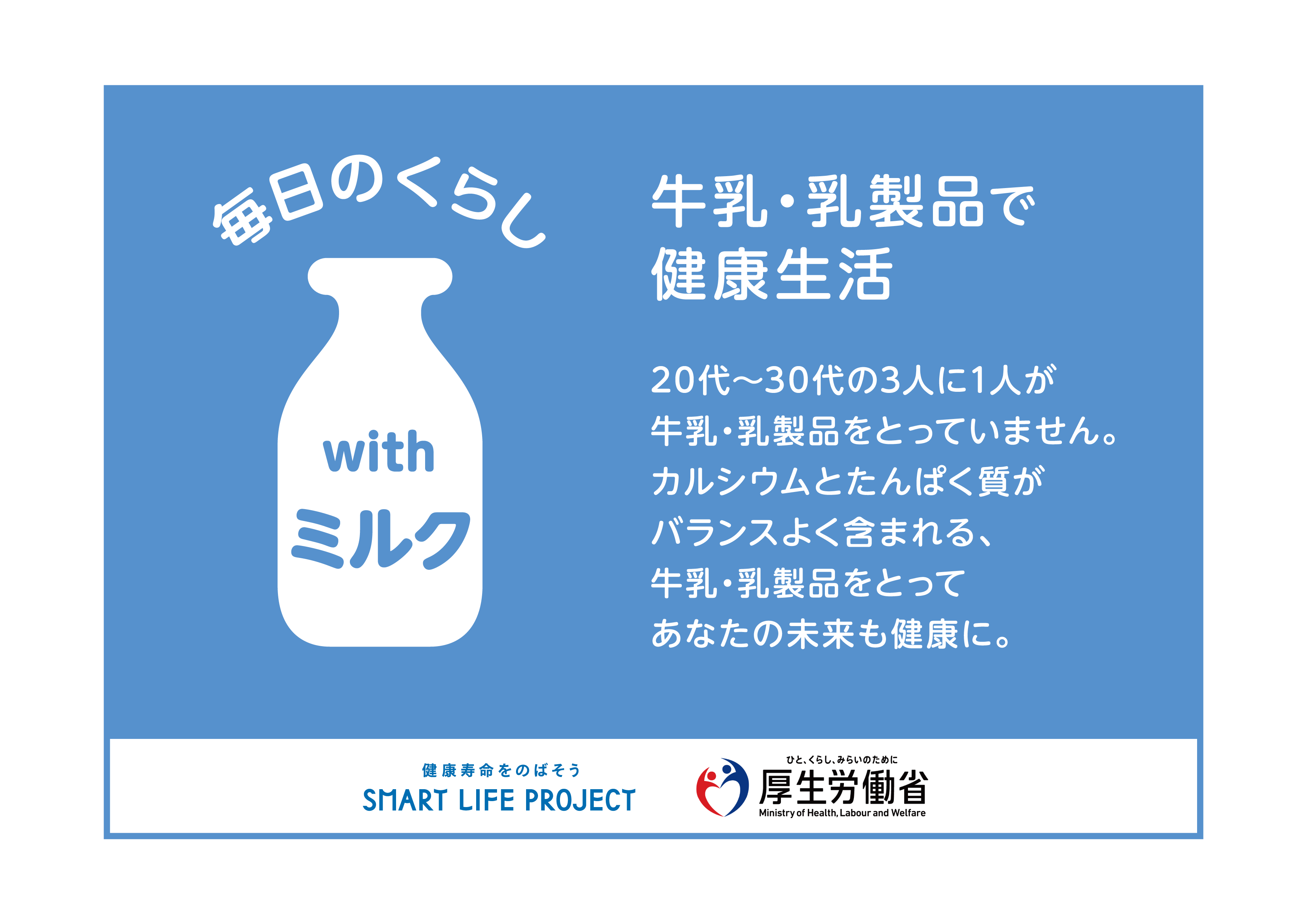
牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品は、骨の健康維持や筋肉づくりに欠かせないカルシウムなどのミネラルやたんぱく質を豊富に含んでいます。
成人の骨密度は20歳頃にピークを迎え、その後減少し始めるため、年代問わず乳製品の摂取は将来の骨密度を守るために大切なことです。
食事やおやつに取り入れ、1日1回以上を目安にしましょう。