この運動は、暖房機器の使用等により火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、町民皆様の火災予防思想の一層の普及を図ることで火災の発生を防止し、お年寄りや身体の不自由な方を中心とする死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的とし、実施されます。
火災予防運動期間中、消防署及び消防団による火災予防広報を実施します。
実施期間
令和7年10月15日(水曜日)から10月31日(金曜日)まで
防火標語
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」

住宅用火災警報器(住警器)の点検はしていますか?
住警器は設置から年数が経過している場合、経年による劣化で、正常に作動しない可能性があります。(住警器の寿命は10年程度です。)
いざという時の為に、日ごろから点検し、異常がある場合や10年経過した場合には交換する事を推奨します。

放火火災を防ぐためには
放火による火災は、死角となる場所や深夜帯に多く発生し、発見の遅れにより被害が拡大します。
対策として、屋外に燃えやすいものを置かないことや、自動車等のボディカバーに防炎品を使用することが効果的です。

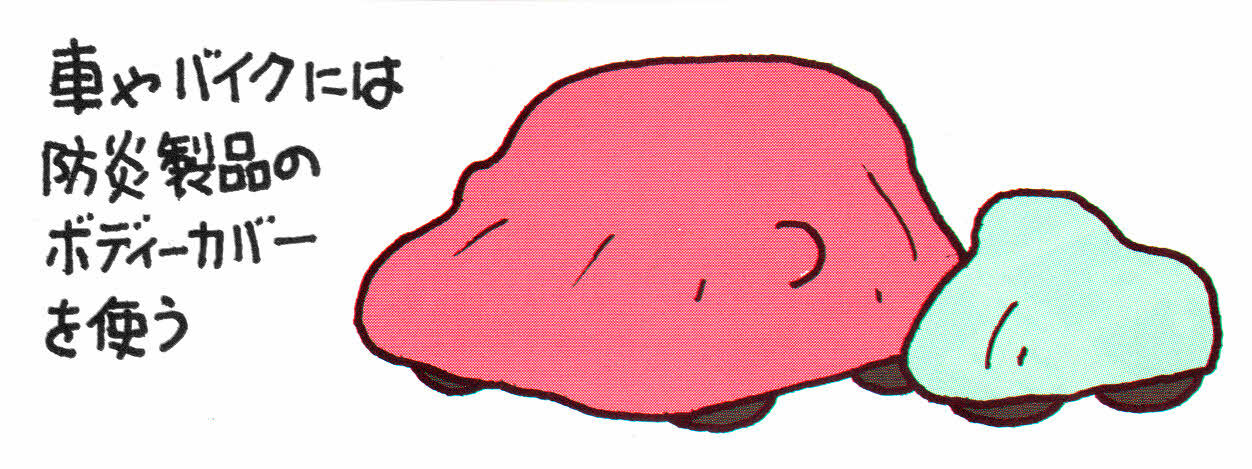
充電式電池について
近年、リチウムイオン電池等の充電式電池に起因する火災が増加傾向にあります。
リチウムイオン蓄電池はPSEマーク等がついている製品を購入して、取扱説明書に従って使用し
電池の膨張など異常が生じた場合は使用を中止して下さい。
また、充電式電池の白老町の廃棄方法については、通電しないよう端子部分にテープを貼り、有害
ごみとして決められた日に廃棄して下さい。
地震火災を防ぐポイント
「通電火災」とは
地震や台風等の自然災害後、停電から電気が復旧した際に倒れていた
電化製品や破損した電源コード等が火元となり発生するのが「通電火災」です。
町内でも、令和7年7月28日に震度3の地震を観測しています。
幸いにも地震による火災は発生しませんでしたが、いつどこで何が起きるか分かりません。
主な対策
1.感振ブレーカーの設置(地震発生時、設定以上の揺れを感知した際に電気を自動的に止める機器)
2.住宅用分電盤の機能充実
(1)漏電ブレーカー (漏電を検知し電気の供給を遮断する機器)
(2)コード短絡保護機能(配線の損傷や短絡を検出し電気を自動で遮断する機能)
停電時・避難時の対応
1.停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く。
2.停電中に自宅から離れる際は、ブレーカーを落とす。
停電復旧時の対応
1.給電再開時は、浸水などにより電化製品が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすい物
が近くにないかなど、十分に安全を確認してから電化製品を使用する。
2.建物や電化製品等には.外見上の損傷がなくとも、壁内の配線の損傷や電化製品内部の故障により、再通電後、
長時間経過した後火災に至る事がある為、煙やにおい等の異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落とし
消防機関へ連絡する。
3.浸水等により一度濡れた電化製品は使用しない。